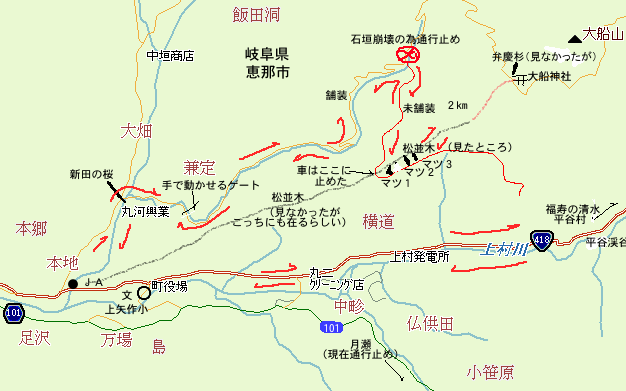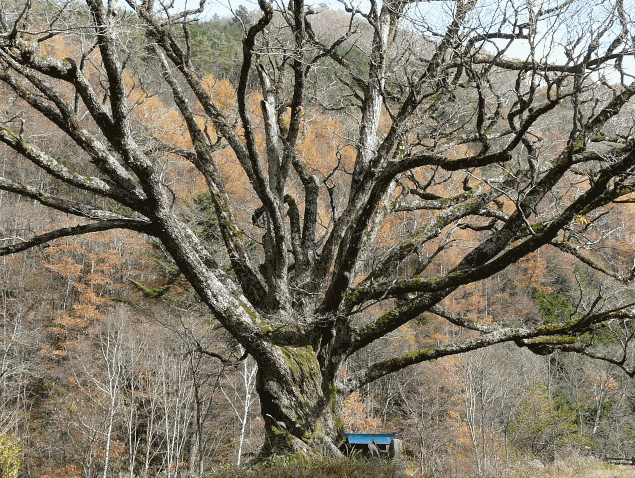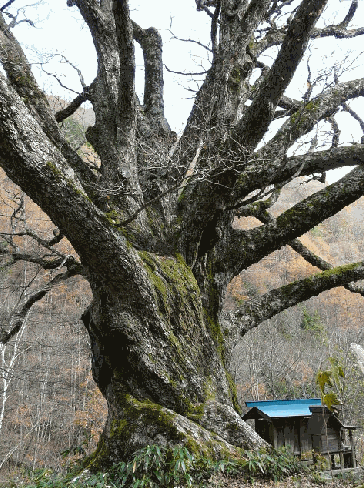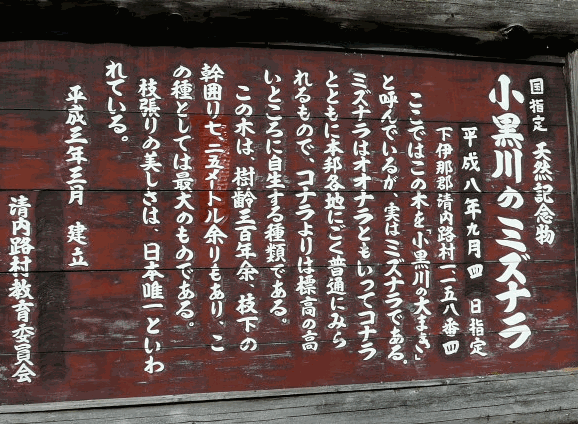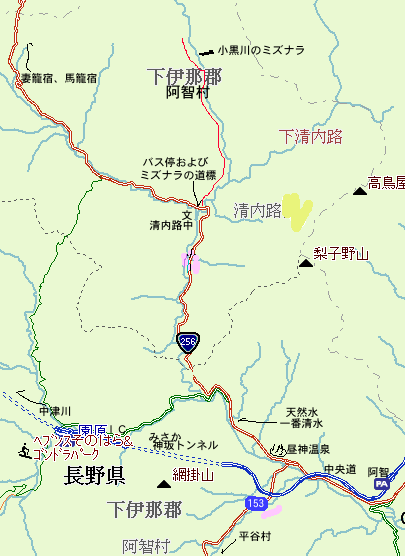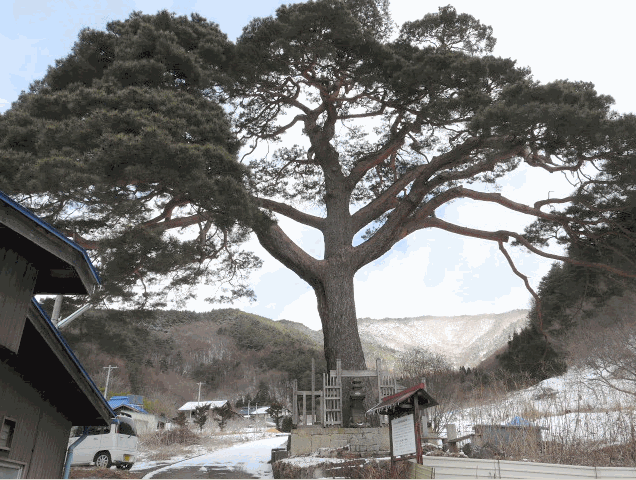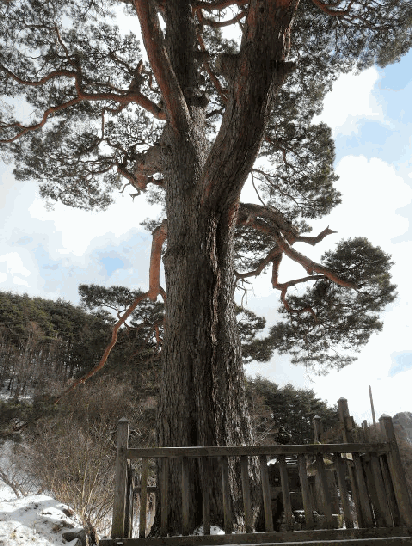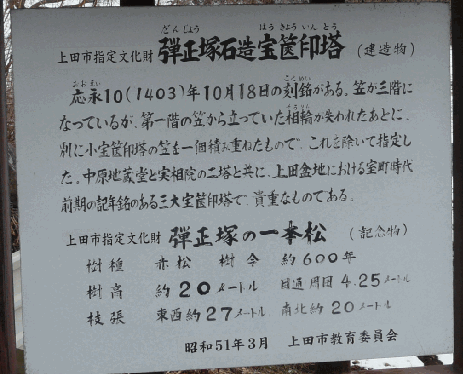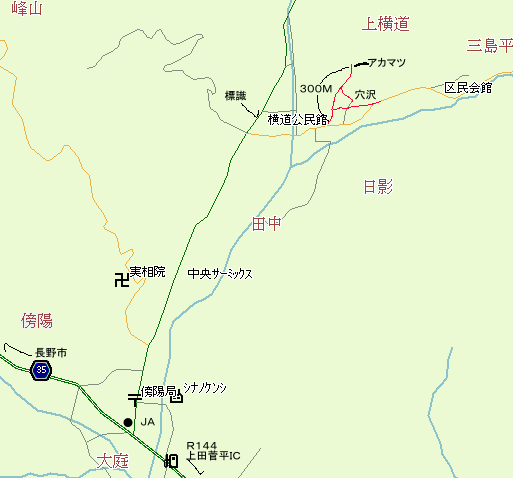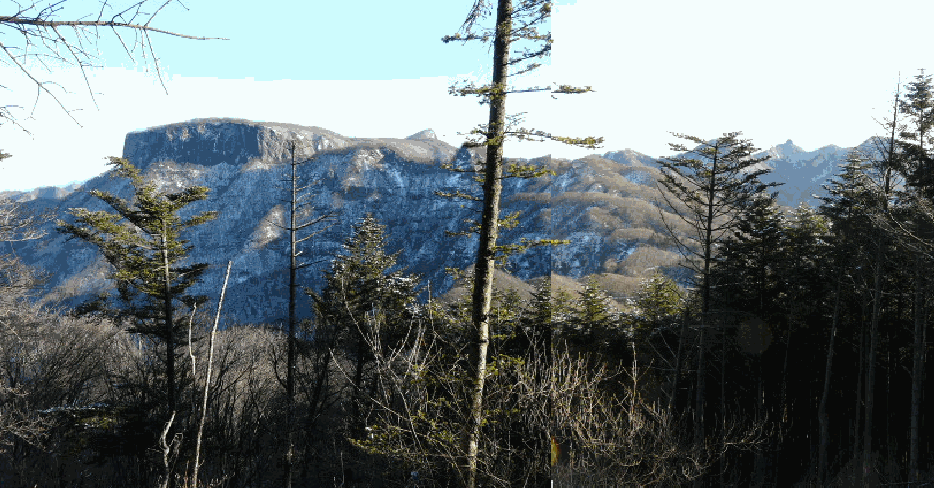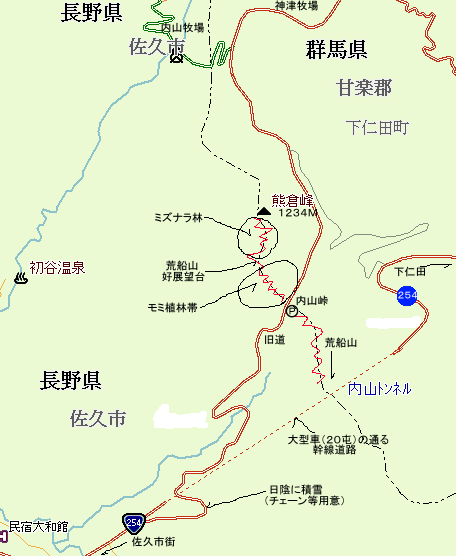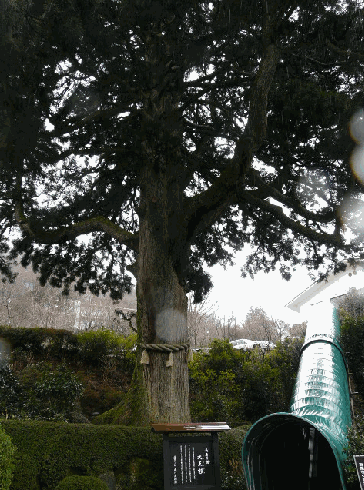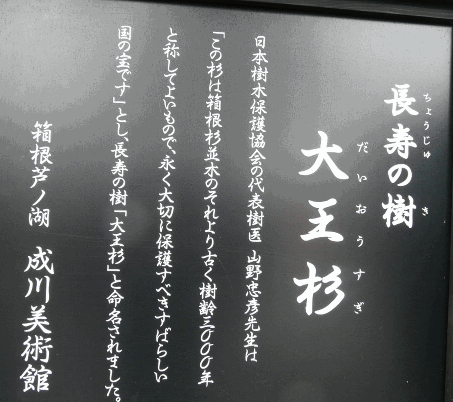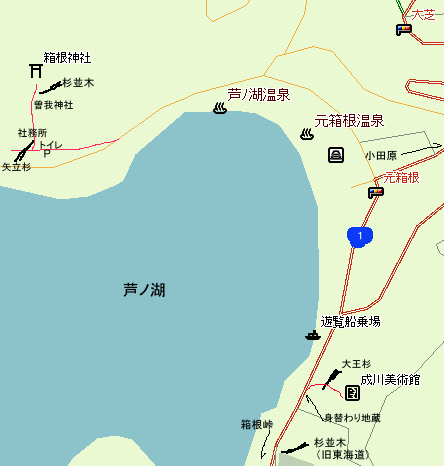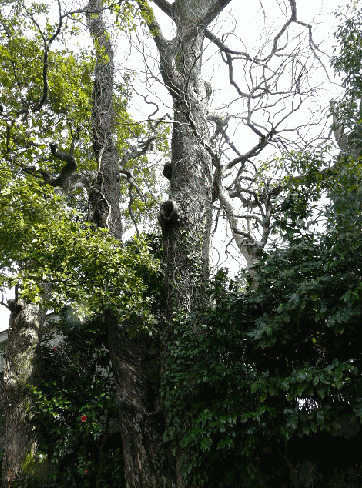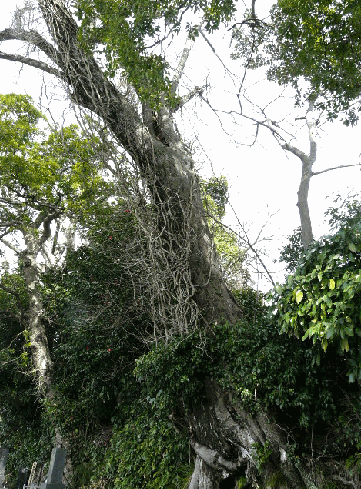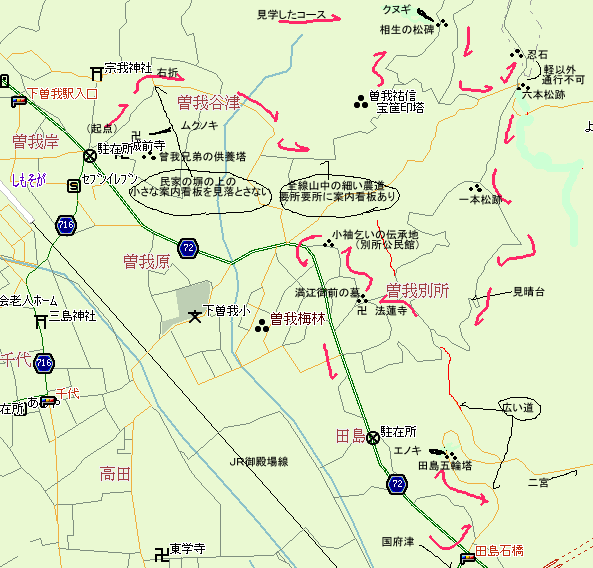愛知県北設楽郡豊根村
茶臼山1415M
(長野県との県境でもある)
ブナ1
目通り 2.5M
樹高 15.0M
ブナ2
目通り 1.6M
樹高 10.0M
内々のことで恐縮だが、家内がどうして
も阿智村の小黒川のミズナラ(日本で
最大で唯一の国天然記念物)を見てお
きたいというので、一泊で奥三河と南信
の樹木の旅を計画した。
ミズナラの前に茶臼山登山(愛知県最
高峰)、根羽村の月瀬の大杉(長野県
最大の樹木、同じく国指定)、上矢作の
大船神社の松並木(昭文社県別マッ
プル23愛知県P65に載っている)を私
の希望で併せて見ることにした。
私のHPは静岡県と山梨県を主たる見
学地と定めているのでこの地域は対象
外で「おまけ」の地域である。
また私にとってはこの地域は生まれて
2度目の旅である。それは今から25か
30年前、長野県から帰る途中伊那を通
って佐久間に抜けようとした時、佐久間
に抜ける途中夜になって方向を失い道
に迷い、しかもガス欠寸前になって地元
の人に助けられてやっと帰宅したという
苦い経験を持っている。
|
いずれにしてもこの地域は静岡市から
はアプローチが大変だ。今回選んだの
は東名で豊川インター、R151で新城市、
その後R32、R10、R473,R257、R1
0、R507で茶臼山にやって来た。朝8
時に家を出て高原の駐車場に着いたの
は1時頃であった。
茶臼山は平ちゃんの山岳巡礼で予備知
識を付けておいた。スキー場があること、
山頂までは30分位であること。駐車場に
車を止め道標に従って歩き始める。山頂
は手に取るように見える。最初は公園と
いうか牧場というかなだらかな尾根を登る。
途中から灌木から樹林帯に変わる。
驚いたのはこの樹林がブナ優勢で、カラ
マツ、ウリハダカエデ、モミ、ツガ、オオイ
タヤメイゲツ、カマツカ、イロハカエダ、ミ
ズナラなどの混合林であった。最大のブ
ナ1は決して大木ではないが頂上のやや
手前で一抱えをかなり余して横に大きく枝
をはっている。来る途中の車道ではまだ
紅葉の綺麗な所もあったが、この付近は
全て落葉していた。
樹林は今は山頂一帯に限られているが牧
場開拓以前は全体がこんな森であったの
かもしれない。歩きやすい道で、樹種の看
板も所どころに付いており確認しながら登
る。山頂は木の展望台があり正面にスキー
場のリフトがはっきり見える。展望台から少
し北に行けば恵那山も見えたかもしれない。
山を下りスキー場の方を見るとリフトの近く
に何やら1本大きな木が立っている。ブナ
かミズナラか?鍵が掛かっていなかったの
で進入禁止の看板を無視してスキー場に
入る。5分ほどでリフトの脇に車を止め木
|
を見るとブナ2であった。しかし入口に戻る
と鍵は閉まっていた。すぐ側に管理の人が
いたので謝って鍵を開けてもらう羽目にな
ってしまった。くれぐれもこんなことをしない
ようにご注意を。
このスキー場は2人乗りリフトが2基500M
ほどありゲレンデも広かった。初心者からや
や上の経験者まで、また家族連れも思った
よりも結構楽しめそうだと感じがした。恵那
山が見えたりして何しろ景色がよいのが何
よりだろう。もう少し若ければ一度位は来て
みたかったと悔やまれる。
2010,11,17撮影
 四代目月の家円鏡は茶臼山北の売木村の出身だそうだ
売木峠へ行く途中の大きな看板
(こういう看板いいですね。親近感を感じます)
四代目月の家円鏡は茶臼山北の売木村の出身だそうだ
売木峠へ行く途中の大きな看板
(こういう看板いいですね。親近感を感じます) |
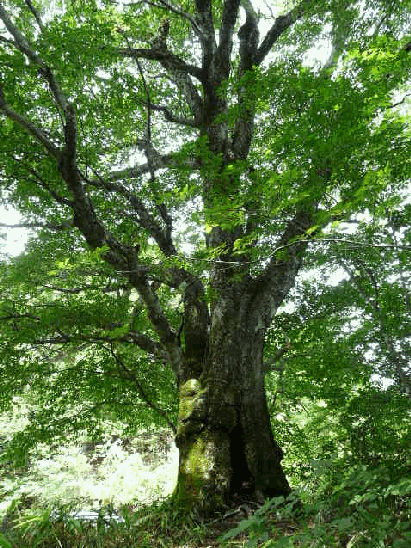

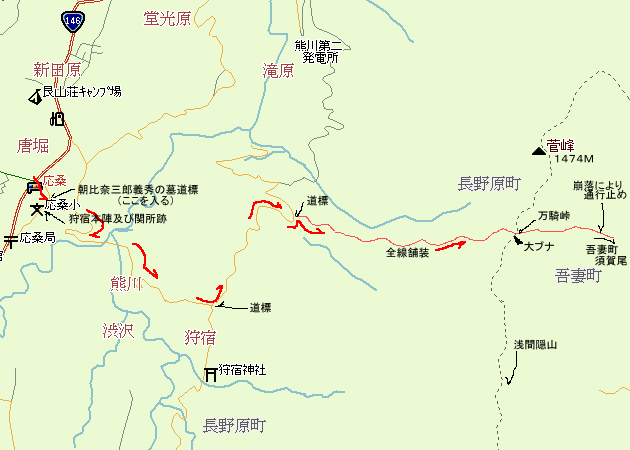
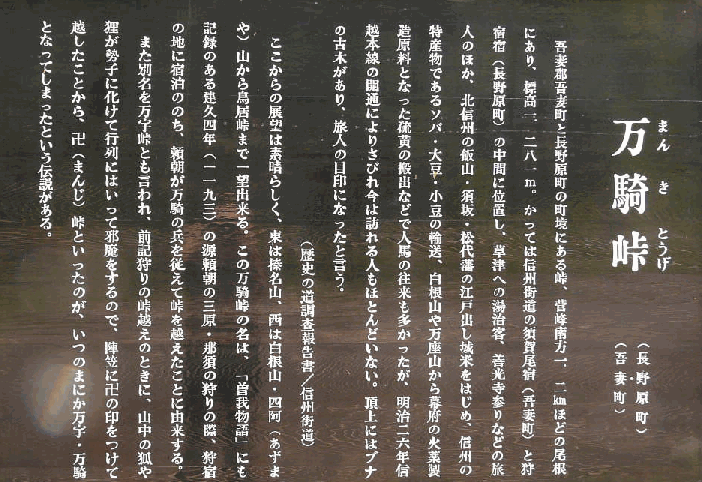





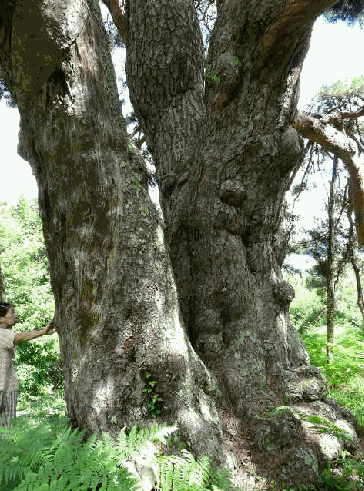
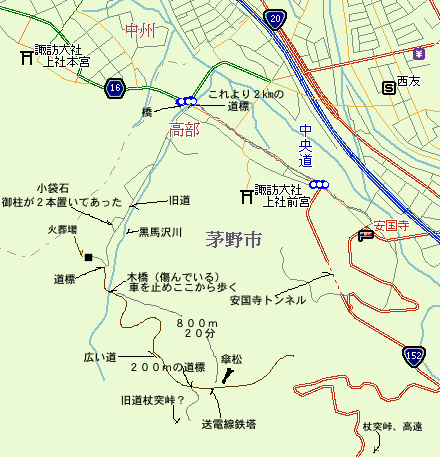
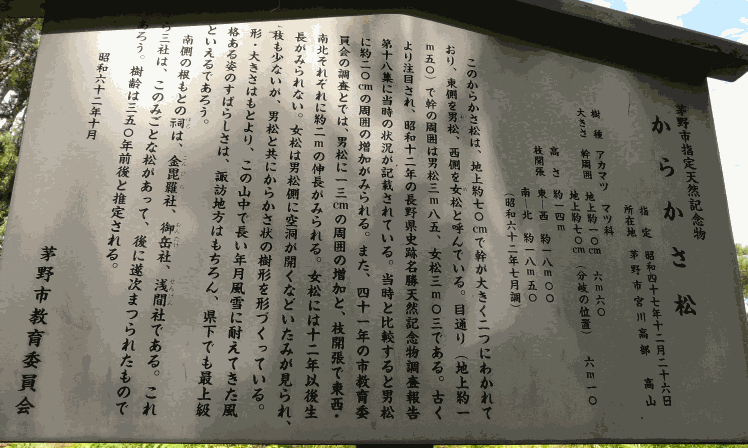




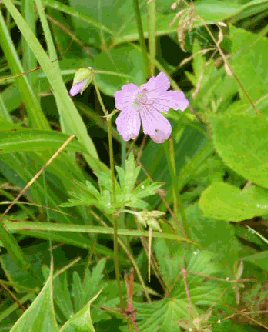

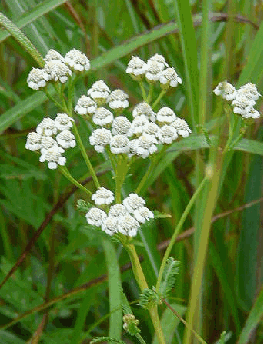

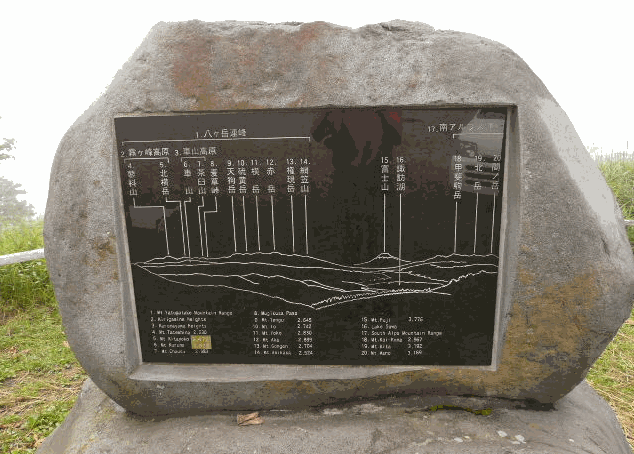




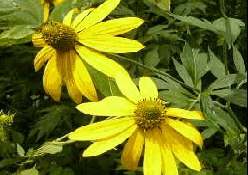
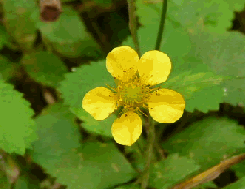

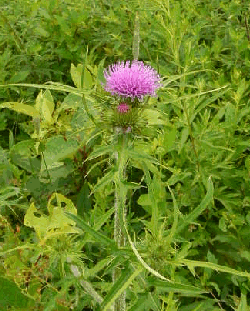
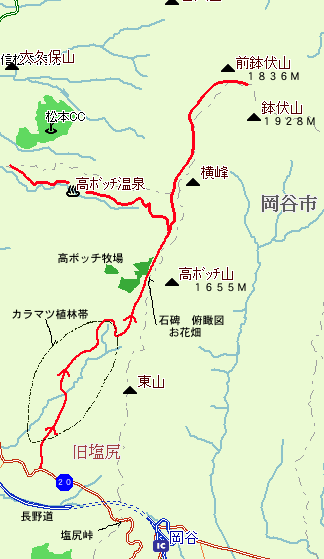



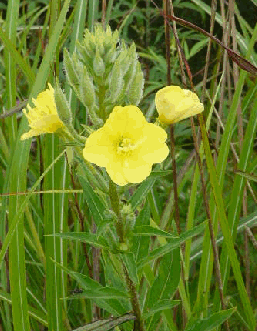 +
+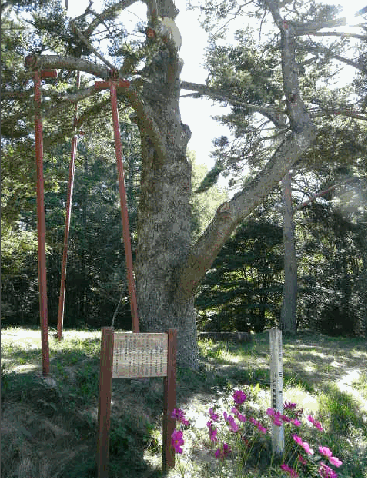
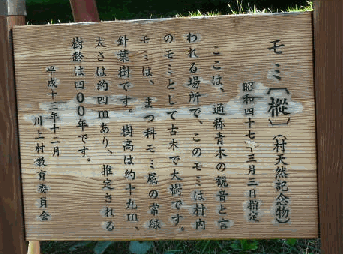

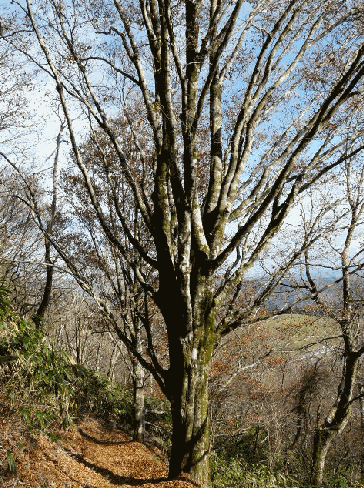
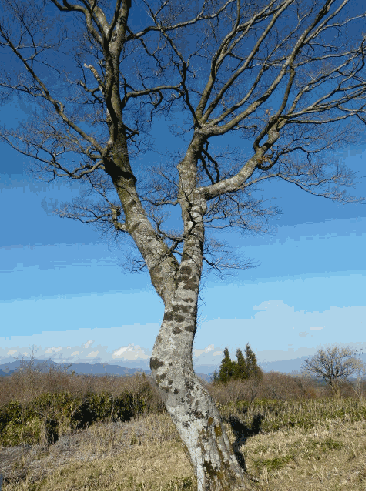


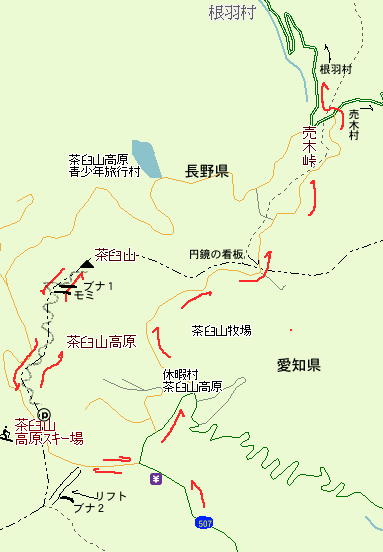
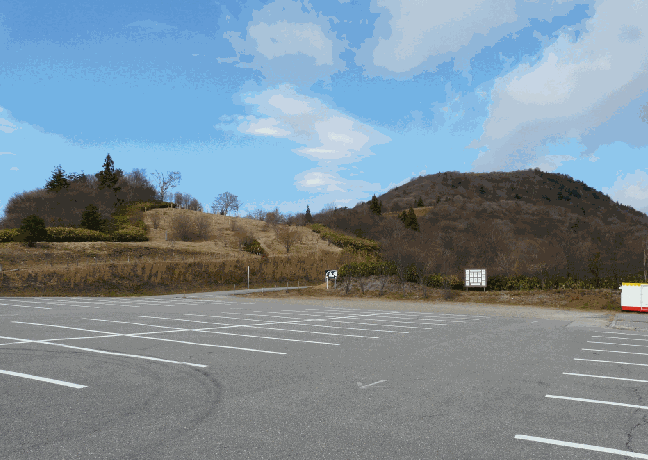













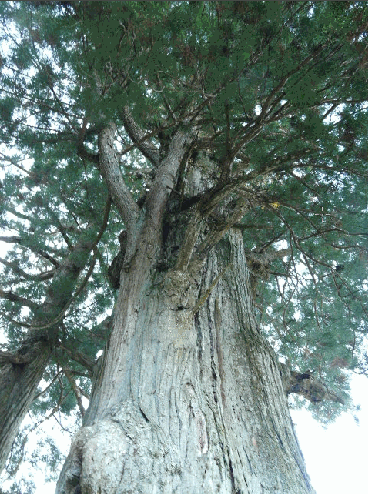
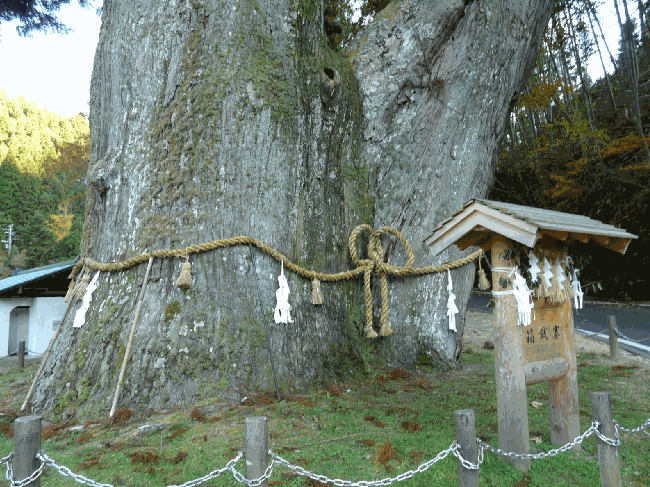
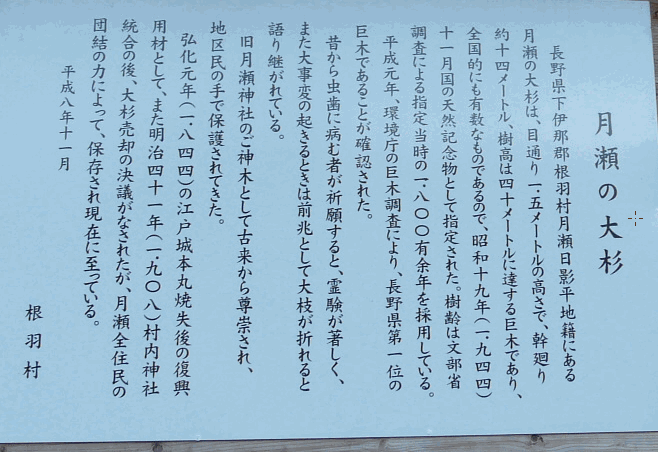
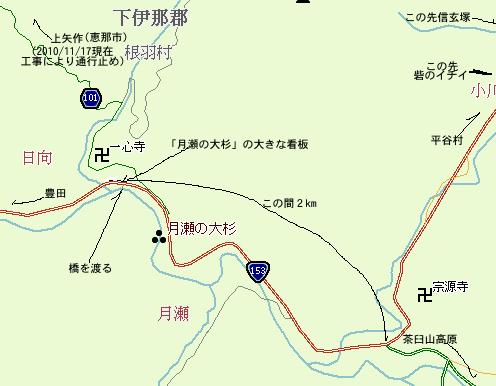



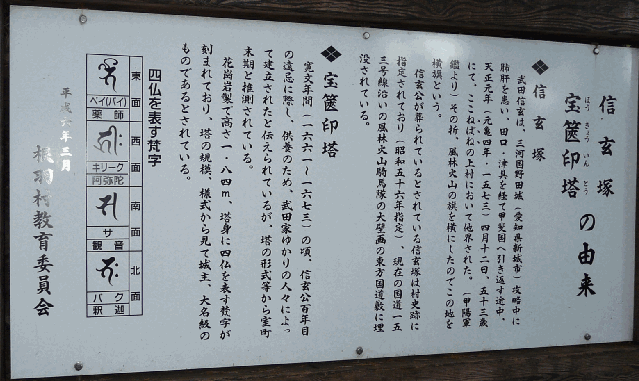

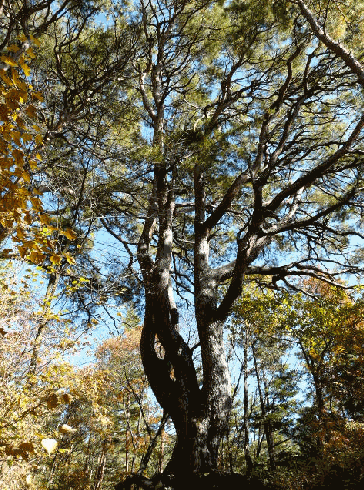
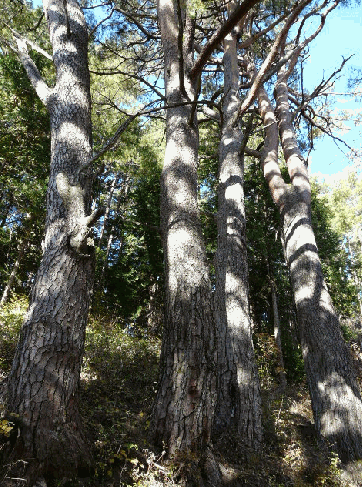




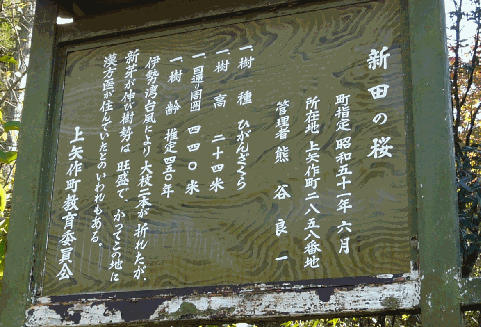 本郷
本郷